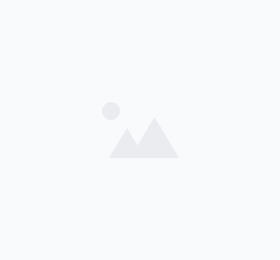『雨の記憶』作 鐘崎那由他
雨の音を聞くといつも天海先輩のことを思ってしまう
私は憧れの学校に入って勉強を頑張っていた。
中間テストの前に残って勉強していたら外は土砂降りになっていた。
「どうしよう。駅まで走る?」
(私は呆然と下足室で立ち尽くしていた。)
そんな時に天海先輩は
「俺家近いから使って」って言って駅の方に走って行ってしまった。
私は唖然として、背中を目で追っていた。
「え、あれってバスケ部の天海先輩?え、どうして?」
でももう先輩の姿は見えなくなってしまっていた。
私はどうすればいいか分からないままに渡された傘を差して駅に向かった。
電車の中でぼーっと傘を見つめていたら時間が止まったように長く感じた。
どうやって帰ってきたのかすら分からないままに家に着いてご飯を食べてベッドに横になった。
ふと我に返って
「この傘どうすればいいんだろう。どうやって返そう。3年生の教室まで持ってく?いやいやむりむり。。。じゃあ下駄箱に入れる?いやいやそれも、、、出来れば直接渡したいし。うぅぅぅぅ〜」(いつまでたっても考えがまとまらない。)
私はお気に入りのくまのぬいぐるみを抱きしめて脚をバタバタしていた。
眩しい陽射しで目を覚ました。
「え、まだ6時前じゃん。私、あのまま寝ちゃったの?え、どうしよう。寝癖もひどいし。」
そうこうしているうちにいつもの時間を過ぎてしまっていた。
「え、もうこんな時間。頭こんなだしどうしよ〜。」
私は慌てて部屋を出て洗面所に向かった。
今日はこの傘返さないと「よし、決めた。授業終わったら下足室のところで天海先輩待っとこう。」
そんなこんなで、今日の授業は頭に入らなかった。
急いで下足室の前に向かった。天海先輩は通らなかった。
「はぁ」っと大きくため息を吐(つ)いて腰を降ろしたとき後ろから声がした。
「あ、昨日の1年生じゃん。もしかして僕のこと待っててくれてた?ごめんね。掃除当番で遅くなっちゃってさ。」っと私が持っていた傘を軽く持って行ってしまった。
少し遠くの方で
「お前またかっこいいことやってたのかよっ」
とクラスメイトとじゃれながら
「だって困ってる子がいたら助けるじゃん。それに可愛かったからさっ」って言い返していて。
私は胸がきゅんとして、自分でも顔が赤くなるのがわかるぐらいに動揺した。その瞬間、天海先輩のことが好きになっっちゃったんだって自覚して恥ずかしさのあまり鞄で顔を隠した。
この出会いが私にとっての叶わない恋になるかもしれないけれど、好きって伝えたいって心に誓ったんだ。